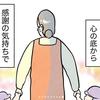海外からも評価の高い、日本の母子健康手帳は、1942年に始まった「妊産婦手帳」が最初。その後様々な改定を経て現在にいたります。乳幼児死亡率の低減に役立つと、インドネシアなど海外にも広まり、現在は30以上の国や地域で使われています。

ややこしい予防接種のスケジュール管理も!広まりつつある「電子母子手帳」が、かなり良さそう!
25,395 View妊娠がわかると、市区町村の役所からもらえる「母子健康手帳」。妊娠した実感がわく、初めてのプレゼントのように感じませんでしたか? 出産証明にもなり、予防接種記録などを記入してずっと使い続けるもので、肌身離さず持ち歩いている方も多いのでは。
しかし、全てが手書きによる記入。もし紛失したらこの貴重なデータはどうなるの?と不安になったこと、ないでしょうか?
日本の「母子健康手帳」は、海外でも評判!?

電子母子手帳って何?
電子母子健康手帳は、従来の母子健康手帳の内容をインターネット上で管理できるもの。
さらに、母親学級や集団健診のお知らせが自動で届いてトップページに表示されたり、子どもの生年月日を登録すると、予防接種の時期が表示されたりするサービスも。
エコー写真や育児日記も保存でき、夫や、両親などとも情報共有できる電子母子健康手帳もあるそうです。
電子母子健康手帳って、もう使えるの?
京都府や大阪府池田市、富山県富山市や南砺市、千葉県木更津市、岐阜県可児市など各地で導入を始めています。電子母子手帳の企画・開発をしている(株)エムティーアイによると、同社のシステムだけでも40~50の自治体が導入準備を進めているそう。東京都でもすでに一部でテスト運用をしています。
なかでも、2014年1月から導入を決め、2016年4月から本格稼働した千葉県柏市の取り組みは、各種メディアに取り上げられて、注目を集めています。今までの紙の手帳が撤廃されるわけではなく、紙の手帳を補完する道具として利用者の評判は上々の様子です。
電子化することのメリットは?
母子健康手帳が電子化される一番のメリットは、紛失によるデータ消失を防げること。
紙の手帳は置き忘れたり、紛失してしまったり、洗濯してしまうなどの可能性のほかに、地震や津波などの災害時にとっさに持ち出せない心配もあります。
東日本大震災でも、多数の方が母子健康手帳を失いましたが、岩手県では妊婦の健診結果などを医療機関や市町村が共有する電子カルテネットワークシステムがあったため、紛失した母子健康手帳の再発行や医療機関の妊婦受け入れが比較的スムーズだったそうです。改めて電子化のメリットが再認識される大きな機会となりました。
ママも、貴重な手帳を持ち歩かなくてもよくなり、そのほかの育児関連の膨大な資料を身近なツールを使用して見られること、予防接種のスケジュール管理に便利など、様々なメリットがあります。
さらに、医療サービスを受ける上でのメリットとして、カルテを多くの病院施設で共有できることもありそうです。
電子化することのデメリットや心配

現状のデメリットは、自治体ごとで導入しているシステムなので、引っ越したり、病院を替えたりしてしまうと、うまく移行できない場合があること。
日本産婦人科医会は、医療機関が扱う出産前後の電子カルテと連携できるようにすることが重要だとして、母子健康手帳の電子化と標準化を目指す「電子母子健康手帳標準化委員会」を2014年1月24日に発足させています。
また、専用のソフトをNTTドコモとNPO法人「ひまわりの会」(東京都)が共同開発中だそうです。
しかし、診療用の電子機器との連携には巨額の費用がかかります。
さらに、パパママは、個人情報の管理、漏洩の心配、そしてスマホやパソコンを持っていなかったり、操作が苦手な人だったりすると、ちょっと大変かもしれません。
これからの発展に期待!
総務省と厚労省でも、個人が登録した母子手帳のデータを医療機関、自治体と共有することで、利用する人が一生使い続けられるシステムにできないか検討中とのこと。
実現すれば、アレルギーの情報や予防接種の状況、かかった病気をどこの医療機関で簡単に参照できることで、よりタイミングよく、適切な治療につながりそうです。
さらに生まれてからの健康に関する詳細のデータを細かく管理することで、生活習慣病の予防や難病の解明につながるなど、幅広い医療研究に役立てられることも期待できそうですね。
電子母子手帳は全国のプレママやママの7割が「利用してみたい」と答えたという調査結果もあります。
紙の手帳が全くなくなってしまうと、少し寂しいかもしれませんが、当分は併用しながら、万が一の時に備えたり、保管できたりするものとして考えれば、とても便利なものになりそうですね!
今後の展開が楽しみです!
#キーワード

2
「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3
寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

話題の「ブレインスリープ」に早まる夏や長引く猛暑から身体を守るクールシリーズが登場

コノビー編集部

え、そこで? 寝かしつけ中の謎ポジション。実は誰もが通る道だった!笑

コノビー編集部
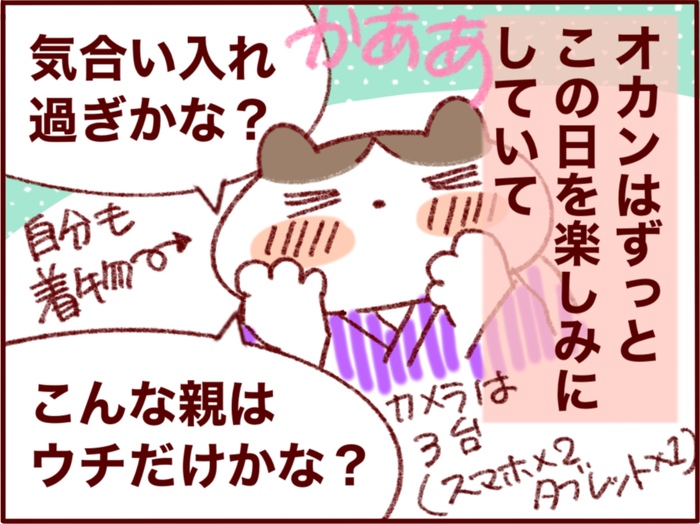
子どもの大切な“節目”の式典。親はどれくらい気合いを入れていく…!?

さとえみ

ごはん中に眠くなってしまった双子。今しか見れない必死な姿にキュン♡

コノビー編集部

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい