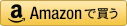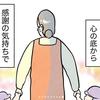こんにちは。今日は、『1人でできる子が育つ テキトー母さんのすすめ』の立石美津子です。
行事だけでなく言葉も、時代とともに変わってきています。“父兄会”は“保護者会”や“父母会”に、“保母さん”は“保育士”などなど。ひとり親家庭の子どもに配慮して“父の日、母の日を廃止する園もあります。
でも、言葉や行事を変えるだけ何かが大きく変わるのでしょうか?

ひとり親家庭のために「母の日」の行事を廃止。それってホントに必要?
61,383 Viewもうすぐ、母の日ですね。そして6月には父の日があります。最近では、ひとり親家庭の子どもも多く、母の日や父の日などの行事を廃止する幼稚園、保育園もあります。実際、父の日に「パパの顏」を描かせたら「離婚している家庭も多いのになんたることか!」とクレームがある話を園側から聞いたこともあります。
例えば、「黒板」という言葉
黒板は1872年にブラックボードという名前でアメリカから入ってきました。実際に黒い板でした。そのため日本語では“黒板”という名前で定着しました。しかし、黒字に白いチョークで書いてある文字は目がチカチカするということで、緑色に変わってきました。
でも、この時点で“緑板(りょくばん)”という名称には変わりませんでした。チョークの粉が舞うので最近はホワイトボードもどんどん普及しています。
私はかつて子どもたちに授業をしていましたが、ホワイトボードを指さして生徒達に「黒板を見ましょう」と言っても特に大きなどよめきはありませんでした。先生が白い板を指して「黒」という言葉を使っても変だとは思わないようです。「先生が勉強を教えてくれる板」であることだけを理解していれば名称なんてあまり気にしない様子でした。
言葉って中身を正しく理解していればそれでいいこと。そんなものだと私は思います。

言葉だけを変える
黒板のように無機質な物体についてはその名称について、世間はそんなに神経質にはならないのですが、人物を表す場合、そういう訳にはいかないようです。男性保育士も男性看護師もいるのでどちらかの性を強調するような言い方もなくなりました。
例えば
・看護婦→看護師
・保母→保育士
・父兄会→父母会・保護者会
・精神分裂病→統合失調症
・精神薄弱児→知的障がい児
・躁うつ病→双極性障害
・落ちこぼれ→授業についていけない子、授業につまずいてしまう子
などです。
「障害児」をどう表記するのか
“障害者の“害”という字が“障害者が社会の害になっているような印象を与える”という理由から、“障碍者”と別の漢字にしたり、“障がい者”とひらがな表記するように変わってきています。“チャレンジド=挑戦する人“と全く違う言い方で呼んでいる団体もあります。たしかに“害”はよくない印象の言葉ですが、言葉だけを変えても、正しい理解をしていなければ結果は変わらないと思います。
例えば、小学校では普通学級と特別支援学級の言葉で区別されています。この言葉を耳にして「僕は普通ではないの?」と質問をしてきた知的障害児がいました。そうなるとこの言い方も変えなくてはならず、きりがありません。
又、運動会で特別支援級の子どもが普通学級の生徒に交じって競技をしたとき「あいつが入ると負けるから嫌だ」と言ってきた普通学級の生徒たちもいました。言葉を変えることだけではなく、“世の中はいろんな人で構成されている”“普通とはどういう意味か”を教育することが大事なのではないでしょうか。

「自閉症」という名称
“自閉症”という言葉は、現在もこのまま使われています。”自閉→自分の心を閉ざしている→鬱みたいなもの”と誤解をされることもあります。精神疾患の代表格である“精神分裂病”が“統合失調症”と名前が変わったように、呼び方を変えてほしいという運動を起こしている人もいます。
実際に殻に閉じこもっているわけではないのですが、コミュニケーションをうまくとることが出来ない、相手の気持ちを読み取ることが苦手である特徴があります。“自分の世界にいる=自閉症”の名称は当たらずとも遠からずの名前だと思います。
「父の日」「母の日」の廃止
近年はひとり親家庭など、複雑な家庭事情を抱える子どもは増加の一途をたどります。「子どもが悲しい思いをしないように」と父の日、母の日を廃止したり、“家族の日”に替えている園もあります。父親参観日をなくして通常の保育参観にしている園もあります。
でも、そうやって子どもに配慮しても「うちにはパパがいない」「うちにはママがいない」という現実は変わらないわけです。
私も息子の通う保育園ではただ一人のシングルマザーでした。園全体で息子のことを考えて「父の日にパパの顔を描かせるのは止めよう」ということになり、園児全員がパパの顏ではなく“家族の顏”を描かされていました。これを見たときは「そこまで気を遣ってくれなくてもいいのに」と正直思いました。
なぜなら、ひとり親家庭の子どもは毎日、どちらかの親がいな環境で育っているので「うちにはママがいない」「うちはパパはいない。ママ一人で僕を育ててくれている」とちゃんとわかっています。シングルのママの人の中にも腫れ物に触るように扱われているような感じがして、私のように却って気を遣われ過ぎて窮屈に思っている人もいたりします。

まとめ
こんな風になると、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんが亡くなっている園児もいるから“敬老の日廃止”、男尊女卑になるから“雛祭り廃止”、“5月5日は子どもの日だから男の子のイメージが強い兜を飾るのは廃止”となってしまいますよね。クリスマスはキリスト教の行事だからとやらない園も実際あります。
私はそんなことはあまり気にしないで実施したらいいと思っています。
余談ですが私が50年前に通っていた幼稚園は神社が運営していましたが、神主さんでもあった園長先生がサンタさんの恰好をして子どもたちにプレゼントを配っていました。また、お寺が運営していてもハロウィンのイベントをやっている保育園もあります。季節の行事によって、子ども達はいろんな文化に触れられてよいのではないでしょうか。
表面的な言葉だけを変えることだけに神経を使うのではなく、“違いを理解して一人一人が多様性を受け入れる”そんな時代になることが何よりも大切だと思います。皆さんはどう感じますか。
#キーワード

1
何度言っても生ごみを三角コーナーに直入れで捨てる夫、遂に妻は……‼

コノビー編集部

2
夫の飲み会にブチ切れた心は、ママ友の"秘密"を知って癒される。

眠井アヒル『ママ友さんとアンコちゃん』

3
旦那のDIY術① 触られたくないものは…こうするっ!これぞ育児の知恵

にくきゅうぷにお/講談社

4
義実家で「ちょ、何この家族…!」夫のルーツは、こんな習慣にあるのかも

コノビー名作集

全母が共感!?子どもは大きくなったのに、母はついやりがちです(笑)

コノビー編集部

たまらんかわいい!仲良し赤ちゃんとダックスくんのわちゃわちゃ♡

コノビー ゆるっとフレンズ

切って貼るだけ!? 超簡単かぶと飾りが天才可愛すぎる♡ミシン不要!

コノビー編集部

禍々しいオーラを放つ、アレはなに…!?子ども部屋で母が白目になるとき

コノビー編集部

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい