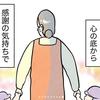小児科の診察室には、多くの子どもとご家族が訪れます。
そして多くの子どもたちに出逢うなかで
わたしがしばしば感じているのは、
子どもには、自分の長所を「自分で褒める力」があるということです。

子どもには、自分の長所を「自分で褒める力」がある。【きょうの診察室】
11,894 Viewみなさんのお子さんは、褒められたときどうしていますか?きょうは、診察室で褒められた子どもの反応から、私が教えてもらったことのお話です。
きょうの診察室:「もしもし、とくいなの?」
診察のなかで、子どもたちにお願いすることの多い「聴診」。
その意味を完全に理解していなくても、
胸に当てられる聴診器を受け止めて、
音を静かに聞かせてくれることは、
とてもすごいことだなぁと思っています。
だからこそ、聴診に協力してくれた子どもたちには、
「わー!すごい。よく聞こえて助かったよ。●●ちゃん、もしもし、得意なの?」
と、気持ちを伝えさせてもらいます。
するとおもしろいことに多くの子どもが、
いわゆる”ドヤ顔”をして
「うん!(得意だよ!すごいでしょ!)」
と誇らしげに頷いてくれるのです。
大人は“謙遜”してしまいがち

みなさんは、「すごいですね、それ得意なんですか?」と褒められた時どうしていますか?
きっと多くの方が、「いやーそんなことないですよ」「そんなこと言ってもなにも出ないですよー」などと、謙遜してしまうことが多いのではないでしょうか。
素直に自分を認める、さらにそれを他者にも伝えることって、大人社会ではなかなかしにくいことなのかもしれません。
そして、それはお子さんが褒められたときや認められたときにも言えること。
「お母さん(お父さん)、●●くんすごいですね!」
素直にその言葉を受け取って、「はい、よくできていますよね!」「わたしもそう思います!」と言えているご家族は、少ないのではないかな、と思うのです。
「認める」といいチームを組みやすくなる
褒めるという行為は、その人を認めるということだと思います。
そして「認める」ということを素直にしていくと、
実は、子どもとの関係性にも変化がうまれてきます。
わたしは診療の際に、うるさいくらいに(笑)子どもとご家族をいっぱい褒めるのですが、
「まっすぐ座れたね!」
「わー、お名前言えてすごいね!」
「”もしもし”、じょうず!協力的!」
「あっ!今日でいちばん大きなお口。」
「よーく見えるなあ、さすが!」
そんな風に褒めれば褒めるほど、
認めれば認めるほど、
子どもたちはわたしとチームになり、
できる範囲の協力をしてくれようとするのです。
診察は子どもとの共同作業。
だからこそ、「あなたのことを認めているよ」ということをたくさん伝え、いいチームを組めればと思っています。
もしかしたらこれは、『子育て』に置き換えても、言えることかもしれませんね。
大人になっても「自分を認める力」を持ち続けてほしい

子どもたちをみていると、人間は生まれながらに、自分を認める力を十分にそなえていることを教えられます。
しかし私たちは大人になるまでの過程で、
集団生活を経験し、
秀でた自分を強調しないように、
目立ちすぎないようにと学習をし、
その力を発揮しないようになってしまう。
もちろん謙遜や控えめであることも、
大切な才能だと思います。
でもきっと、子どものときの自分を認める才能を持ち続けて大人になれたら、人生はもっともっとステキになるんじゃないかな、とも思うのです。
子どもは自分自身を認める力、そして他の人のことも認めてくれる力を持っています。
お子さんが自分自身を褒めたとき、その子のすごさを認め、相槌を打つ。
お子さんが褒められたときは、「ありがとうございます!」と笑ってみる。
さらに、ご家族も便乗して、「パパはこれが得意!」「ママはこれができるよ!」と伝えあってみる。
自分のことも、他者のことも認めあえる文化が、子どもの間にも、大人の間にも広がりますように。
そして、子どもたちが大人になっても自分を認める力を大切に持ち続けられますように。

2
「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3
寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

あっ、花火が笑ってる!4歳児が撮影した奇跡の1枚でみんなが笑顔に

コノビー編集部

指しゃぶりからのうとうと。それだけなのにどうしてこんなに可愛いんだろう

にくきゅうぷにお/講談社

知育教材なんて...と思ってたものの!?結構楽しんでます、4歳児

ぺえかあちゃん

これが子どもの発想力…!娘に「何を描いたの?」と聞いたらすごかった…

おやま/KADOKAWA

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』