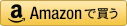「子どもの遊びを止めない」には、実は2つの意味があります。
ひとつは、子どもの遊びを「くだらない」と思って止めないで!ということ。子どもに対してよくやりがちなのが、子どもの遊びを止め、大人が遊びをすり替えてしまう行為です。
意外にも、子どもに慣れた人に多いのですが、外出時に、子どもがお店に置いてあったおしぼりをいじって、せっかく自分なりにおもしろさを味わっているのに、「ほら、こっちにおもちゃがあるわよ!」と、既製品のおもちゃを出して、「はい、どうぞ!」とおしぼりを取り上げてしまう。あるいは子どもがおしぼりに集中しているのに、注意をひくために、話しかけてしまう。
自分が一生懸命何かをしているときに、他人が突然入ってきて、ちがうことをすすめてきたら……?
誰だって不快になりますよね。遊びのすり替えはそれと同じ。
子どもは特に、一見何をしているのか理解しがたい動きも多く、大人は、それが実は大切な行為の最中だと気づかない。

無意識のうちに、子どもの「遊び」をすり替えていませんか
42,859 View書籍「いい親よりも大切なこと~子どものために“しなくていいこと"こんなにあった!~」(著:小竹めぐみ・小笠原舞)より、全7回にわたり、「親子がもっとハッピーになれるヒント」をご紹介します。第4回目は、「子どもの遊び」について。
子どもの遊びをすり替えないで


夢中になっている「遊び」は、大きな「学び」。
どうか、「遊びとはこうしたもの」という思い込みを取っ払ってみてください。大人の都合や感覚で、遊びをすり替えるのは、子どもにとっては本当に悲しいことなのです。
ただし、遊びに使ってほしくないもので遊びだしてしまったときは、話は別。
本当は、それを子どもの手の届かないところに置いておければ一番よいのですが、うっかり……ということって、ありますよね。危ないもの・大事なもの・汚いもの……(だって、ウンチで遊ばれたらいやですよね!)。
いくら子どもが関心を持っていても理由があってやめてほしいのなら、もちろんやめさせて構いません。ただ、「どうせまだ、理解できないし」と思わずに、必ず理由を伝えてあげてくださいね。
遊んでいたものを「ダメ!」と突然取り上げてしまうのは、子どもにしてみれば、いきなり宝物を奪われるようなもの。もちろん、危険なときは別ですが、「人としてやられていやなことは子どもにもやらない」ようにしたいものです。
子どもだってひとりの人間です。わからなくなったときは、常に、自分だったらどう感じるか考えてみましょう。
子どもは急に止まれない

「子どもの遊びを止めない」のもうひとつの意味は、「はい終わりーっ‼」と、子どもに急に遊びをやめさせないで、ということ。時間の感覚が大人とちがう子どもたちは、「やめられない」のです。
「もう遊ぶの終わり!寝るよ‼」と、電気を消してみても、子どもは気持ちがなかなか切り替えられず、泣き続けたりしますよね。こんなシチュエーションで大変な思いをしたママは多いと思います。
「遊びの止め際って難しい。いつまでも遊びを続けていられては生活ができないけど、いい方法がわかりません」そんな悩みをよく聞きます。
では、こういった場合には、どうすればいいのでしょうか。
まず、遊びをやめさせたいときには、「今からブロック?すぐご飯の時間だよ。ご飯ができたらやめられるかな?」と、前もってやりとりをしておきましょう。「うん、いいよ」となれば、時間になったとき「さっき決めたよね」と言うと、小さい子どもでも比較的納得してくれます。
また、特に3~5歳に向けては、遊びの始まり方と終わらせ方をちょっとイメージしてみてください。たとえば、うちの子はこの遊びは比較的サッとやめるけど、これをやり出すと長い、というのがあると思います。
「あの人は居酒屋で飲みだすと長い」とか、「メールは短いが電話は長い」のように、大人だっておんなじですよね。
子どもが「ブロックを始めたら時間がかかる」というのであれば、「ご飯が〇時だから、今からブロックをやっても〇時には終わらないといけないよ」と伝えてみる。
その上で、「今はブロックじゃなくて、こっちで遊んだら?」「ブロックは、ご飯を食べ終わってからゆっくりやろうよ」などと提案してみましょう。
こういった見通しを立てることができるのは、大人だからなのです。いつでも子どもに自由に選ばせてしまうのではなく、シチュエーションに合わせて、声をかけていきましょう。
達成感を壊さない
4歳の子どものママの話です。子どもが一向におもちゃを片付けてくれず、「このまま、ずっと片付けられない子に育っていってしまうのでは」と心配していました。
でも、考えてみてください。“片付ける”ということは、子どもからしてみれば、つくった世界をリセットすることなのです。
子どもが一番悲しいのは、自分の意思じゃないのに、大人の都合だけで、自分の大事なものを片付けられてしまうこと。
大事にしていたものを、勝手に誰かに捨てられてしまったという経験がある方は、気持ちがわかるのではないでしょうか。それと同じです。
ブロックでつくる基地がまだ完成していなくて、この後、また続きをつくりたいというときもあります。それなのに、無理やり片付けさせてしまうと、どういうことが起きるでしょう。
子どもにしてみれば、「やりきった」という達成感を得られないまま、いやいやリセットをすることになるのです。そんなことが度重なると、達成感を経験せずに育っていくので、途中で投げ出すということが染み付いてしまいます。それでは、大人になったときに困ってしまいますね。
そのママにちょっぴりアドバイスをしたところ、片付けをその都度しなくてもいいスペースをつくってみたそうです。「ここのスペースなら、出しっぱなしにしてもいいよ」と、時間的にはやめさせても、また続きから遊ぶことができるということですね。
すると、子どもはやりかけのおもちゃをきちんとそのスペースに置くようになりました。これまでは、子どもが片付けないことにイライラしていたママ自身の気持ちも晴れて、穏やかに過ごせるようになったそうです。

ちなみに、0・1・2歳の子どもは、また少しちがいます。時間の感覚や、記憶力が、まだまだ備わっていないので、遊びをリセットされても気にしない、ということが比較的多いのです。
この達成感について、親はいつから意識して対応すればいいのか。それは、子ども本人がリセットされることを気にし始めたら考えてみてください。やりきらせてあげること、つまり本人の納得感が大事で、本人が「もういいや」となればいいでしょう。
園に勤めていた頃よく使っていたのは、できあがったものを写真に撮るという方法です。「写真も撮れたから片付けようか」というと、満足そうに片付けを始めることができました。
そうやって、子どもの遊びを止めないようにするために、色々なやり方を試してみてください。「どうしてあげたらいいのかな」と思いを巡らせる時間こそが大切なのです。

2
「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3
寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

これが子どもの発想力…!娘に「何を描いたの?」と聞いたらすごかった…

おやま/KADOKAWA

話題の「ブレインスリープ」に早まる夏や長引く猛暑から身体を守るクールシリーズが登場

コノビー編集部

え、そこで? 寝かしつけ中の謎ポジション。実は誰もが通る道だった!笑

コノビー編集部
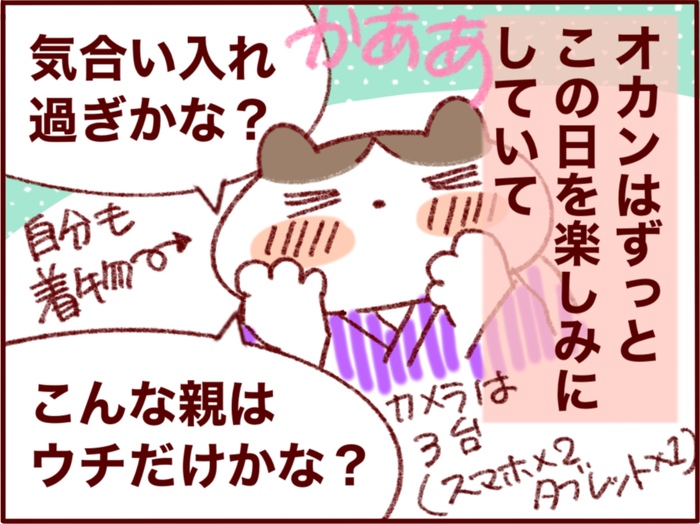
子どもの大切な“節目”の式典。親はどれくらい気合いを入れていく…!?

さとえみ

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい