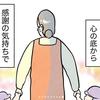みなさん、こんにちは。プレイワーカーの関戸です。
前回のコラムでは私の主な仕事のフィールドである冒険遊び場(プレーパーク)についてご紹介しました。

自分で自分にOKが出せる「根拠のない自信」が育つ環境とは〜子どもの遊びと育ち(心編/自己肯定感)〜
166,232 View日本は自己肯定感の低い子どもたちが多いと聞きます。その原因がどこにあるのかはっきりとは分からないものの、子どもたちが遊ぶ現場にいて感じることはたくさんあります。豊かに遊ぶ経験を持った子どもたちに共通している”根拠のない自信”とは?遊びが子どもたちの心の育ちにどんな影響をもっているのか。エピソードを交えながら紹介していきます。
今回は、私の仕事のキーワードでもある「自己肯定感」について、現場でのエピソードを交えながらお話したいと思います。
自信のない日本の子どもたち
まず、次の表を見てください。

これは日米中韓の高校生の自己肯定感に関する調査なのですが、日本は他の国に比べて突出して肯定的な回答数が低いのが見て取れます。高校生という多感な時期である点、日本特有の気質で「謙遜すること」が美徳として扱われる点などの影響もあるでしょうが、それらを差し引いたとしてもかなり低い状況ですね。
実際に私が遊び場で関わる子どもたちの中にも、遊びに誘われても「ボクには(私には)できない・やったことない」が口癖で、頑なに新しいことへのチャレンジに消極的という子に何人か出会います。
自分にも、そして自分のやることにも自信がないため、「意欲がなく、対人関係を築くことも苦手」な状態になってしまっているのです。上記の表の結果や私が出会う子どもたちの状態は、実は子どもの遊びのあり方と密接に関わっていると私は考えています。
他者評価でなく、子どもが自分で自分にOKが出せる“根拠のない自信”を

私は2004年から8年間、渋谷区にある「渋谷はるのおがわプレーパーク」という常設の遊び場でプレーリーダーをしていましたが、長男が1歳半になった2012年3月に退職し、その後2年間は家庭で長男と過ごす、いわゆる「主夫」生活を経験しました。
午前中は毎日のように近所の公園に遊びに出かけていたのですが、その帰り際になって息子がブランコに乗り始めた時によく「しまった!」と私は思っていました。心境としては「買い物があるのに長引くなぁ」「早く帰ってお昼寝させたいなぁ」といった類いのもので、「じゃあ、30回だけね!」や「あと5分ね!」と私の都合で区切りをつける声かけもしていました。
しかし面白いことに、特に私が声をかけなくても何度かブランコをこいだ後に(「よしっ!」というスッキリした表情をして)「行こうか!」と自分で下りてくる時があるのです。
こういった彼なりの基準で(何かに)満足した瞬間を、2年間の主夫生活の中でたくさん見させてもらうことにになるわけです。時にそれは大人の私にはわからない価値観であると同時に、彼の世界で丁寧に重ねられてきた彼だけの大切な価値観でもありました。
「遊びきったかどうか」は大人が決めるのではなく、子ども自身が決めるものだということを、仕事に復帰したその後も様々な子どもたちからも学びました。また、遊びきる経験を積み重ねてきた子どもたちの心の成長もたくさん見せてもらいました。
遊びきる体験を多くすることで、自分で自分にOKが出せるようになってくるのです。
この自信は他人と比べることができない主観的な評価に基づくものであって、「かけっこで1位」「どろだんごづくりが他の子よりも上手」といったことを他人に褒められるなど、客観的で相対的なモノサシを経て得た「優越感」とは大きく異なります。私はこれを「根拠のない自信」と呼んでいます。
子どもはたくさんの自由な遊び体験を通して、自分で自分にOKが出せるようになるための主観的なモノサシを育んでいます。それがあってはじめて、人は自分を好きになる気持ちを育てることができるのです。
「自信のなかったAくん」と、たった30分間の「野球の時間」
私が冒険遊び場でプレーリーダーをしている時のこと。カラーボールとカラーバットを持った一人の男の子が「野球やる?」と声をかけてきました。彼はAくん。当時小学校2年生ぐらいだったと思います。
Aくんは、遊び場に来ても、いつもなぜか私を含めたプレーリーダーの大人としか関わろうとしませんでした。他の子たちとは口もきかず、目線すら合わせようとはしませんでした。
私たちプレーリーダーも毎度のAくんの野球の誘いにすべて応じられる訳もなく、一日の中でタイミングが良い時に30分ぐらい一緒に野球をするという感じでした。そしてその30分以外はずっと、プレーリーダーの後ろを着いてウロウロとするばかりで、他の遊びに誘っても頑なに拒否。遊びの輪に入ってくることはありませんでした。
ただ、野球をしている時の彼は活き活きとしていました。Aくんは常にピッチャーで、バッター役のプレーリーダーに向かって、決して上手くはないけれど全力でピッチングをしてきました。その僅かな時間を思いっきり楽しむ。そういった日々が続きました。
そんなAくんでしたが、次第に変化していく様子を見ることができました。
ある時期を境に、野球をする時に、プレーリーダーが誘った他の子どもたちとであれば、簡単なやりとりをしたり、目を合わせたり、ある程度コミュニケーションをとることができるようになってきたのです。

Aくんが遊び場に通い始めて1年を過ぎたころには、依然として、他の友だちに他の遊びに誘われても「おれはできないからいいよ」と言って、少し離れて見ているだけでしたが、一緒に野球をした経験がある友だちとであれば、少し話ができるようになっていました。
Aくんが鬼ごっこやトランプなど、野球以外の遊びを他の子どもたちと一緒に楽しむようになったのは、それからさらに数年後のことです。
最終的には、自分から声をかけて、野球や他の遊びに子どもたちを誘うこともできるようになりました。Aくんを中心とした子ども集団ができることなど、当初からは考えられなかったのですが、確かに長い月日の中でAくんは何かしらの殻を破り、自らを成長させる機会を掴んだのでした。この変化は劇的な変化ではありませんでしたが、着実に積み重なっていった変化でした。
初めて会った時からしばらく経って知ったのですが、Aくんは遊び場のある学区に住んでいるわけではなく、土日だけ、電車に乗って遊びに来ていたのだそうです。当然、遊び場の周辺に見知った友人がいるわけでもなく、「遊び場がある」という話を頼りに一人で遊びに来ていたのです。
そこにどんなスタッフ(大人)がいて、どんな子どもたちが来ているのか全くわからない状態で、同い年くらいの子どもたちに声をかけるのは誰だって尻込みしてしまいますよね。遊び場に初めて来た当時小学2年生のAくんにとって、唯一自信を持って遊びきれるものは、スタッフとやる30分の「野球」だけだったのかもしれません。
子どもの遊びを見守り、「待つ」ことで生み出せる環境がある

何が楽しいかを決めるのは、遊んでいる子ども本人です。「上手にできたね」や「すごいね」といった声かけは子どもにとって嬉しいものではありますが、本来は誰かに認めてもらいたくて遊んでいるわけではなく、ただただ「楽しくて仕方がないから」遊んでいるのです。
こういった夢中で遊んでいる状態の子どもは、自分自身の満足をたくさん感じられる体験を重ねています。満足の基準は、一人ひとりの子どもの中にあります。泥だんごであれば、光るほどに綺麗に磨くことに満足を覚える子もいれば、数をたくさんつくることに一生懸命な子もいます。また、つくった泥だんごを食べ物に見たてて遊ぶことで、盛り上がる子など…、楽しみ方は人それぞれです。
このように、「自由」に遊ぶことができる環境は子どもが自分の人生の主人公として輝くためになくてはならない大切なものなのです。
親も、幼稚園・保育園の先生も、街ゆく人も、みんなが忙しい現代社会。子どもたちが自分自身で「遊びきった!」と思えるだけの経験を積み、その積み重ねの中で確かな自己肯定感を育んでいくためには、何かを与えたり関わることを考える前に、まずは大人の方が余裕を持ち、少し「待つ」こと。それ自体が、実は立派な環境づくりになっているのです。
次回のコラムでは
ただ、「少し待つ」というのが難しいんですよね。分かっていても、なかなかできないということがあると思います。
次回は「子どもの遊びと育ち(心編―自己肯定感)」の第2弾として、自己肯定感を育むための子育ての具体的なコツ(親同士の関係性づくり、ナナメの関係)について、私自身の主夫生活でのエピソードを紹介しながらお話していく予定です。お楽しみに!
#キーワード

2
「お母さん…」しめじを調理しようとした娘の言葉に、衝撃が走る!

コノビーおすすめ書籍

3
寝返り時期あるある。できるようになるとあちこち挟まるから助けるの大変

にくきゅうぷにお/講談社

4
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

知育教材なんて...と思ってたものの!?結構楽しんでます、4歳児

ぺえかあちゃん

これが子どもの発想力…!娘に「何を描いたの?」と聞いたらすごかった…

おやま/KADOKAWA

話題の「ブレインスリープ」に早まる夏や長引く猛暑から身体を守るクールシリーズが登場

コノビー編集部

え、そこで? 寝かしつけ中の謎ポジション。実は誰もが通る道だった!笑

コノビー編集部

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』