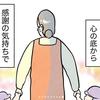今から35年ほど前まで、重度障害といわれる子は、養護学校(今の支援学校)でさえ、入学を拒まれていたことをご存知でしょうか?
1979年に養護学校が義務化される前までは、就学猶予や就学免除といって、学齢期に達した子の保護者に対し、学校に就学させる義務(就学義務)を猶予または免除しますね、と子ども本人や保護者の気持ちを聞かずに決められていました。言い方を変えれば、学校に通うことを認めてもらえなかったのです。
そんな頃に、大阪では、そうした子どもたちを受け入れていた学校がありました。それが、大阪の「ともに学び、ともに生きる」教育の始まりだろうと思います。

障害があると入学を拒否!?大阪で行われている「ともに学び、ともに生きる教育」の秘密
4,233 View大阪の教育は、「ともに学び、ともに生きる教育」 を基本としています。それについて紹介させていただきながら、インクルーシブ教育って何か?を考えてみたいと思います。
出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272002458障害があると入学拒否!?
障害のある子もない子も同じ教室で学ぶ実践のスタート
大阪の枚方市では、その頃、「重度障害児学級」というのが、設置されたそうです。
最初は、障害のある子ばかりを集めて一つの教室で過ごします。今のように支援学級などない時代ですから、教師の数も足りません。17人の児童を2人の教師が担当する形でスタートしたそうです。子どもたちは、じっとしていませんから、すぐに教室を飛び出す子もいて、教師一人が授業を行い、もうひとりの教師が子どもを追いかける毎日だったそうです。
やがて、一部の教科は、障害のない子どもと同じ教室で学ぶようにしてみたのだとか。その時に、思いがけないことが起こっていきます。
子ども達は、お互いに刺激を受けあって…
同じ教室で過ごしていると、大人の想像を越えて、様々な子ども達同士のやり取りが起こっていきます。以前のコラムでも、私の娘の運動会での出来事を記したのですが、娘の周りでは、他にもステキなことが沢山ありました。
あるとき、娘がディズニーランドの曲が好きだからということで、子どもたちが休み時間に「ミッキーマウス・マーチ」や「小さな世界」の曲を笛で吹いてくれていました。上手に吹けない子は、娘に聴かせる為に一生懸命練習してくれたそうです。音が乱れていると、娘は、逆に怒ってしまうこともあるので、子ども達は真剣だったようです。その話を聞かせてくださった担任の先生からは、「おかげで、うちのクラスの子どもたちは、笛が上達しましたよ」と。
また、娘は言葉もしゃべれなかったので、周りの友達は、娘が「なんで怒ってるのだろう?」「何が悲しいんだろう?」と、よく娘の気持ちを考えてくれていました。中学の担任の先生からは、クラス懇談会時、「ちぃちゃんが、なんで怒ってるんやろう?なんで泣いてるんやろう?と思うようになったことで、クラスの子ども達が、ちぃちゃんに限らず友達の気持ちを考えるようになった。」と話してくださったこともありました。
他の障害児の親御さんからの話にも似たような話が出てきます。よく聞く話は、自分の子のかけっこが遅い分、周りの子達が一層頑張るようになり、同じリレーチームの子ども達のタイムが、どんどん上がっていくのだとか。そして、障害のある子の方も、友達と同じことがしたくて、真似をして、訓練では何度やってもできなかったことをあっさりやってのけるようになったのだとか。
実際、私自身、そのようなことは、いつも実感してきました。そして、刺激を受けるのは、子ども達だけでなく、大人も同じでした。
大阪の「ともに学び、ともに生きる教育」 とは、子どもだけでなく、大人も一緒に学ぶこと
子ども達のそんな姿を見せつけられて、親である私自身も、何度も考えを改めました。同じように、先生方も、入学時や新年度におっしゃっていたことと意見が変わっていくことがあり、大人の方も、子ども達から様々な気づきをもらう機会があります。娘が地元の小中学校へ通う中で、よかったなぁ~と思えたことの一つは、そんな瞬間に何度も出会えたことです。(娘は、支援学級在籍だった為、支援級で過ごす時間もあったのですが、主に普通級で過ごしていました。)
そうして、子どもや大人が、違いを認め合い、相手の気持ちを考えることが一層上手になれば、障害のある子だけではなく、どの子にとっても居心地のいい学校生活を送ることができるのだと思います。
社会で障害のある子だけがしんどい思いをしているわけではなく、外国にルーツのある子や、両親が揃っていない子、リストラや家族の介護、様々な事情を抱える家庭の子どもたちがいます。障害のある子も一緒にと考えてこられた先生方は、その瞬間瞬間に一番しんどい子の気持ちを中心に考え、クラス運営をされてきたようです。どの子も大切にされる学校では、不登校になる子はあまりいません。
大阪で基本としている「ともに学び、ともに生きる」教育は、40年程前から、障害の有無に関わらず《同じ場で過ごしてきた子ども同士の関わり》を実践されてきたことが大きいのでしょう。そして、障害のある子のための教育ではなく、障害の有無に関係なく集団の中で一人ひとりを大切に、ということだと思います。
とはいえ、大阪の中でも『常に同じ場で』を実践されてきたのは、一部の地域や一部の学校だけです。ただ、インクルーシブ教育そのものは、同じ場で、ということのようですから、その大阪の(或いは他府県での)一部の実践こそが、今、世界でインクルーシブ教育といわれている実践と、ほとんど変わらないのではないか?ひょっとしたら、その最先端かも?と思っています。
これからは、日本中がインクルーシブの時代になっていきます。障害のある子だけが別の場で過ごしていれば、それが当たり前に思えることでしょう。ですが、どの子も同じ場で過ごしていれば、やはり、それが当たり前になっていきます。かつて、障害があるという理由で学校に入学できなかったことを当たり前としていた時代から、今、どの子も学校に通うことが当たり前になっているように。
誰にとっても生きやすい社会の実現には、障害のある子もない子も一緒の場で学ぶ教育が当たり前に実践されていく必要があると思っています。ぜひ、皆さんも考えてみてください。

1
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

2
イメージは、優しくト~ントン…寝かしつけの理想と現実、こんなに違った!

コノビー編集部

3
これは泣く……!新社会人の息子が出発前に振り向いて……

コノビー編集部

4
外で「お父さん」は恥ずかしい。でも無視はよくない…息子は父になんと声をかける?

コノビーおすすめ書籍

連続寝返りができるようになると、必ずこのトラップにハマる

にくきゅうぷにお/講談社

キャラもの入園グッズは、値が張るけれど…買ってよかった!と思う瞬間

そらこ

前髪を切った日、保育園にお迎えに行ったら幸せになった

おやま/KADOKAWA

コツコツ貯めたお金の使い道は?息子さんの優しさが泣ける……(涙)

コノビー編集部

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』