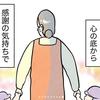働きながら子どもを育てているわたしにとって、忘れられない人がいます。
第一子の産後、約1年の育休を経て仕事に復帰したときのことです。
配属されたのは出産前とは違う部署。
Nさんという先輩が指導役につき、慣れない業務を親切に教えてくれました。
自身も小学生のお子さんがいるNさんは、明るく面倒見の良い女性。
ちょっとお節介すぎるところもありました。
体調が少し悪くてデスクでうつむいていたとき、Nさんに「大丈夫?今日はもう帰りな!ほら、早く」とうるさいくらいに促され、仕事もそこそこに早退させられたことも。
彼女はいつも「育休後の1年はリハビリ期間みたいなもんよ。今までどおりに働けないのは当たり前。ほどほどに働いてたらいいのよ」と、カラカラ笑いながら言うのでした。
はじめてNさんの考え方を聞いたとき「なんて無責任なこと言うんだろう」と、許せない気持ちがあったのを覚えています。
妊娠前はどちらかというとブラックな働き方をしていたわたし。
時短勤務で早く退社したり、突然休んで周りにフォローしてもらったりするワーキングマザーを少し疎ましく思っていました。
わたしは、他のワーママみたいに人に迷惑をかけるような働き方はしないのだ。
子どもがいない人と変わらない成果をあげたい。
そんな気負いがあったのかもしれません。
Nさんの言葉を背中で聞き流しながら、私は自分の仕事を着実にこなしていました。

ワーキングマザーは迷惑…?変わるきっかけをくれた女性上司の話<第三回投稿コンテスト NO.102>
9,175 View出産後も、以前と変わらず、バリバリ働きたいと考えていた、あみちさん。しかしある時、疲労がピークに達し、大事な会議をすっぽかしてしまい…。女性上司にかけられた言葉が、救いになったお話です。

復帰して数ヶ月ほど経ったある日の朝。
着任してはじめて大きな仕事を任され、ときどき残業もしながら頑張っていた矢先のことです。
子どもの夜泣きがひどかった時期で、ちょうど自宅の引っ越しで荷造りに追われていたことも重なって、疲労がピークに達していました。
保育園の送り出しは夫にお願いしたから、自分も軽く家事をしてから出社しよう…とソファに腰かけたところで、意識がふっとんでいました。
気がつくと、時計の針は11時近く。
始業時刻はとっくに過ぎています。
それどころか、午前中に大切な打ち合わせがあったような…。
顔からサーッと血の気が引くのを感じました。
“せっかく周りの信頼を積み重ねようと頑張ってきたのに、最悪だー”
心臓をバクバクさせながら職場に電話すると、Nさんの元気な声が聞こえました。
「最近無理してたもんね。大丈夫大丈夫。こういうときフォローするために私がいるんだから。今日もう休んじゃえば?アハハ」
明るく笑い飛ばすその声に、どれほど救われたことか。
それ以来、他人に迷惑をかけないように意地を張るのはやめました。

周囲の力を借りる。
無理をしない。
つらくなったら早めにSOSを出す。
子どもを育てながら働くためにとても大事なことです。
Nさんがいなければ、学ぶことができなかったかもしれません。
それから1年ほど経ち、わたしの仕事も軌道に乗ってきたころ、Nさんは体調を崩して休職。
その後、退職してしまいました。
わたし以外にもたくさんの同僚を気づかい、時には上司との調整にも入っていたNさん。
彼女の心労は計りしれません。
Nさんにもらった優しさは、今度はわたしが新米ワーママのフォローをして返していきたいと思っています。
(ライター:あみち)

1
多忙な母が、いつも“床掃除”を欠かさなかったワケ…今ならわかるんだ。

コノビー編集部

2
イメージは、優しくト~ントン…寝かしつけの理想と現実、こんなに違った!

コノビー編集部

3
これは泣く……!新社会人の息子が出発前に振り向いて……

コノビー編集部

4
外で「お父さん」は恥ずかしい。でも無視はよくない…息子は父になんと声をかける?

コノビーおすすめ書籍

連続寝返りができるようになると、必ずこのトラップにハマる

にくきゅうぷにお/講談社

キャラもの入園グッズは、値が張るけれど…買ってよかった!と思う瞬間

そらこ

前髪を切った日、保育園にお迎えに行ったら幸せになった

おやま/KADOKAWA

コツコツ貯めたお金の使い道は?息子さんの優しさが泣ける……(涙)

コノビー編集部

思わずキュン…♡レストランで夫の対応に”惚れ直した”出来事

多喜ゆい

夫の育児にモヤる瞬間。「妻がいる前提」のおでかけムーブが私の顔を虚無らせる。

いそめし ちかこ

子が夫に質問「ママのこと大好き?」聞き耳をたてていたら、嘘でしょ…?

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』

「ワーママの大変さ」を、パパが実感したのはこんな瞬間

なおたろー『育児戦隊 ごきげん夫婦』